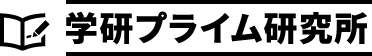「小論文ってどう書き始めればいいの?」
「自分の書き方で合格できるかどうか不安……」
多くの総合型選抜で試験として課されるのが「小論文」を。でも、受験する方の多くはこのような悩みを抱えているのではないでしょうか。
とくに総合型選抜では、小論文試験の成績は合否を大きく左右します。しかし、これまで学校で習ってきた「作文」とは異なる小論文特有の書き方に、戸惑う受験生が多いのが実情です。
そこで今回の記事では、小論文の基本的な書き方から実践的なテクニックまで、具体例を交えて詳しく解説します。学校推薦型での受験を考えている方にも役立つ内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
総合型選抜の「小論文」試験の特徴は?
小論文試験は、文章力を測るだけのものではありません。受験生の思考力や表現力、社会への関心度まで、多面的に評価されます。ここでは、小論文試験で求められる力と評価のポイントを見ていきましょう。
なぜ小論文が重視されるのか?
とくに総合型選抜では、学力試験だけでは測れない「考える力」「表現する力」を評価することが重要視されています。総合型選抜で行われる小論文では、受験生が自分の考えを論理的に組み立て、説得力のある文章として表現できるかを測っているのです。
作文とどう違う? 小論文の評価ポイント3つ
作文と小論文の大きな違いは「主観的な文章か、客観的な文章か」です。作文は「自分がどう思ったか」を書きますが、小論文では「論理的に筋道を立てて、自分の考えを述べる」必要があります。小論文の対策をする際には、以下の3つのポイントを意識しましょう。
・論理的思考力
・問題発見・解決力
・表現力
3つの要素は、どれか1つが欠けても説得力のある小論文にはなりません。普段から新聞やニュースに触れ、自分の意見を持ち、考える習慣をつける必要があります。以下、1つずつ見ていきましょう。
論理的思考力:主張とその根拠が適切に結びついているか
意見を述べるときには「なぜそう考えるのか」を明確に示すことが重要です。たとえば「高齢者の就労支援を推進すべきだ」という主張に対して、「労働力人口の減少に歯止めをかけられる」「高齢者の社会参加が健康寿命を延ばすことにつながる」といった具体的な根拠を示す必要があります。
問題発見・解決力:課題の本質を理解し、具体的な解決策を提示できるか
表面的な問題だけでなく、背景にある本質的な課題を理解しているかが問われます。机上の空論ではなく、実現可能な解決策を具体的に示すことも効果的です。このとき、すでに実施されている取り組みや、他国の事例なども参考にすると説得力が増します。
表現力:自分の考えをわかりやすく伝えられているか
正しい日本語の使用はもちろん、文章の構成や展開の仕方も重要です。1つの段落で1つの論点を扱い、段落間のつながりを意識することで、読み手にわかりやすい文章になります。
小論文の主な出題パターンと対策法
小論文の出題形式には大きく3つのパターンがあり、形式に応じた対策が必要です。
・テーマ型(意見論述型)
・課題文型(文章読解型)
・資料・データ分析型
適切な対策を行うために、まずは各パターンの特徴を理解しましょう。
テーマ型(意見論述型)の特徴と対策
与えられたテーマについて自由に意見を述べる形式で「環境問題について論じなさい」「教育改革の在り方について述べなさい」といった出題が典型的です。
この形式では、主張の独自性よりも、意見の論理性と具体例の適切さが求められます。時事問題や社会課題について、日頃から自分の考えをまとめておきましょう。
課題文型(文章読解型)の特徴と対策
提示された文章を読み、その内容を踏まえて自分の意見を述べる形式です。課題文について正確に理解するだけでなく、適切な解釈・考察をする必要もあります。
対策としては、新書や新聞の社説を読む習慣をつけ、文章の要旨を把握する練習を重ねることが有効です。
資料・データ分析型の特徴と対策
グラフや統計資料を読み取り、導き出される問題点や解決策について論じる形式です。数値やデータの正確な読み取りはもちろん、それらを根拠として用いながら論理的に文章を展開する力が問われます。統計資料などのデータ解釈をする練習をしておきましょう。
合格につながる!小論文の書き方テクニック
実際の小論文作成では、論理的な構成と説得力のある表現を意識することが大切です。ここでは、合格者が実践している具体的なテクニックを紹介します。
論理的な文章構成の組み立て方
序論・本論・結論の3部構成を意識し、読み手にわかりやすい文章を心がけましょう。
・序論:問題提起と自分の立場を明確にする
・本論:具体例や根拠を示しながら論を展開する
・結論:主張を再確認し、全体をまとめる
1つの段落で1つの論点を扱うことを意識して、文章を組み立ててみてください。
説得力を高める具体例の示し方
抽象的な主張を書くだけでなく具体的な例を示すことで、主張に説得力を持たせましょう。具体例を示す際は、「なぜその例を選んだのか」「どのように主張と結びつくのか」を明確にすることが重要です。
▼例
環境問題は深刻で、早急な対策が必要です。企業は環境に配慮した取り組みをすべきです。
▼改善例
私は、企業による環境配慮型製品の開発を促進すべきだと考えます。たとえば、ある日用品メーカーは2022年からプラスチック容器を植物由来の素材に切り替え、年間約1,000トンのCO2削減を実現しました。このように、製品開発の段階から環境負荷を考慮することで、企業活動と環境保護の両立が可能になります。
よくある失敗パターンと改善方法
典型的な失敗には、以下のようなものが挙げられます。
・主張が曖昧
・根拠の不足
・文章が冗長
改善のポイントは以下の通りです。
・主張を冒頭で明確にする
・一文は80字程度を目安に区切る
・感情的な表現は避ける
・客観的なデータや事例を用いる
このポイントに則って、例文を直してみましょう。
▼例
若者の運動不足が問題になっていて、これは本当によくないことだと思います。スマートフォンの普及とともに外で遊ばなくなってしまったり、運動する機会が減ってしまったりしているので、何か対策を考えなければならないと思います。
▼改善例
若者の運動不足は深刻な問題です。調査によると、20代の週1回以上の運動実施率は45.5%で、10年前と比べて15ポイント低下しています。この状況を改善するため、職場や学校での運動機会の創出が必要です。
このように客観的なデータを用いることで、説得力のある文章に改善できます。また、一文を短くすることで読みやすさも向上するので、ぜひ試してみてください。
総合型選抜の小論文で合格を勝ち取ろう!
合格につながる小論文に仕上げるためには、論理的思考力と表現力がカギです。主張と根拠を明確に示し、適切な具体例を用いることで、説得力のある小論文が書けます。
専門的な指導で効率く小論文対策をしたい方は、「学研推薦・総合型選抜ゼミ」をおすすめします。
「学研推薦・総合型選抜ゼミ」の特長
・実践的でわかりやすい映像授業
・経験豊富な講師陣による指導
・段階的な学習で確実に実力アップ
経験豊富な講師陣による映像授業、丁寧な添削指導を組み合わせた効果的な学習プログラムで、あなたの文章力を確実に向上させることができます。総合型選抜、学校推薦型選抜専門のカリキュラムでしっかり対策して、合格への近道を見つけましょう!
難関大へ、推薦・総合型で進学しよう!