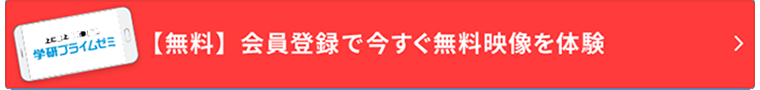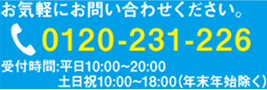数学の共通テスト対策
- ホーム
- 数学の共通テスト対策
小山功先生が攻略ポイントを解説!
“共通テスト「数学」の傾向と対策”
過去問から出題されやすい問題を把握して訓練しよう
共通テストは文章量が多く、典型的な問題を素早く解答していく必要があります。そのためには、分野ごとの理解度を上げておく必要があり、それは分野ごと、さらにその中に含まれる主要なテーマごとの対策が必要です。
自分の学力によって対策は異なりますが、あまり知識やコツが定着していない状態では、細かくテーマごとに区切られたもので一つ一つしっかり理解していくことが大切です。例えば、学研プライムゼミの練成ユニットのテキストを使ってもよいですし、各種予備校から出版されている分野ごとの基礎的な問題集を使ってもよいでしょう。それをある程度こなした後に、過去問や問題集を用いて分野ごと(大問ごと)対策していきます。
共通テストとはいえ、過去のセンター試験で問われた内容が出題されやすいので、過去問から出題されやすい問題を把握しておくことが必要です。なぜなら、それは60分や70分のセットの訓練よりも分野ごとの訓練の方が把握しやすいからです。それが終わったら、過去問、試行調査、問題集などで実戦的な訓練をしていきます。
実戦的な訓練は11月や12月からでも遅くはないので、春から夏の時期はとりあえず各分野を一つずつ深く理解していくことを心がけてください。
数学の共通テストの攻略ポイント
攻略ポイント1:メモすることで明文化を
問題が解けたかどうかではなく、問題で何が大切なのか、それはどう考えていくことで解けているのかという問題ごとのポイントを言葉で自分の中に入れていきます。書くことでよりよく考えられるようになるので、メモすることをケチらない方がよいでしょう。
攻略ポイント2:分野(テーマ)ごとに対策
数学全体で得意・苦手と思うのではなく、二次関数、三角比、確率などの分野ごとに考えます。その上で、各分野の中で細かい内容(二次関数なら軸の位置で場合分け、解の配置など)ごとにできるかどうかを確認します。各分野を一つずつ対策できるようにしましょう。
学研プライムゼミ「共通テスト対策講座」はココがすごい!
何から始めていいのか不安な人にも自信をもって勧められる講座です
まず、各分野に分けた上で、分野の中でも細かなテーマごとに区切って例題を用意しつつ、きちんと理解できるように補足事項を豊富につけています。 例題も充実しており、どのようなテーマが出題されているかを把握した後、実戦的な問題で基礎知識、誘導の読み方などを訓練していけるように構成しています。 テキストが参考書になるように構成してあるので、自学自習もしやすく、何を使って勉強したらいいかわからない人に自信をもって勧められる講座です。
共通テスト対策も学研プライムゼミ!
2021 年度入試からスタートした共通テスト。センター試験と大きく問題形式が変わった部分もありますが、問題を解くのに必要な基礎的知識を重視している点は大きくは変わりません。1979年に始まった国公立大の共通第1次学力試験から40年余り、練り上げられた良質な出題に対する受験対策は、共通テストだけに限らない基礎力養成の意味での高い学習効果も期待できます。
受験対策指導に実績のある実力派講師たちによる学研プライムゼミの共通テスト対策講座で、合格をつかんでください。
学研プライムゼミの講師たちによる科目別共通テストの攻略ポイント解説は、下記のページからご覧いただけます。